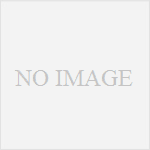昨日スタジオ・バミ企画 寺子屋vol.6~松本方哉さんを迎えて 「介護をめぐる3つの柱」が終了しました。
松本氏の凛としたお人柄が滲み出る、抑制の効いた語り口でありながら、体験されてきたことであるが故の熱い思いが盛り込まれ、報道と分析のプロフェッショナルだからこそのお話は、本当に一言一言聞き逃したくないと一生懸命聞きました。
私は一番後ろの席にいたのですが、参加してくださった皆さんが思い思いに頷きながら聞いていらっしゃるのを見て、誰もが引き込まれているのを感じました。
私にとって、松本氏の置かれた状況に共感することが沢山あります。
我が相方のやましんも、松本氏の奥様と同じくも膜下出血で十数年前に倒れました。
それだけでも他人事とは思えないのですが、奥様が倒れた時に息子さんは5年生だったということは、今の我家で私が突然倒れた状況になるのだと思うと、その大変さはいかなるものかと想像するのが恐ろしくさえあります。 また奥様の2つ目の病気と、亡き母が患った病気は部位は違うものの、同じ問題にぶつかるということ。
奥様のことを自分に置き換えた時、言葉を失ってしまいます。そして息子さんが介護の担い手として、大きな役割をこなしていること、これは想像以上でした。
「今に生きる、先は考えません。」と仰っていた松本氏の言葉。
今の私は山を越えて、自分の事にエネルギーを注ぐことのできる幸せな状態です。それでも、文句言ってる・・・、恥ずかしいです。
母が亡くなった10年前から、約7年間、私にとっては辛い年月でした。
とても言葉には出来ない、「自分」という要素は全く無くして生きていないと、気が狂ってしまいそうな日々でした。
先は全く見えず、ただただ死ぬわけにはいかない、子どもにこれ以上辛い思いはさせられないから、と這い蹲っていたような時間でした。
一体いつから、あのトンネルのような時間から抜け出したんだろう?
松本氏のお話を聞いて、あの時のことを思い出しました。のどもと過ぎれば・・・ではないけれど、私にとってあの時間は「過去」になっています。でもあの時があったから、今がある。
介護については、また次にじっくりと書きます。
以下は、延期になった3月の寺子屋の前に書いた文です。
(松本氏のお話を聞いて、アップすることにしました。)
私事で大変恐縮ですが、ちょっと重い話です。
私は3歳の時から母方の祖父母の住んでいた与野(現在さいたま市中央区)に、両親と共に引っ越してきました。
入り婿になったわけではなかったのですが、土地を利用して父が小さな医院を開業することになり、もともとあった古い建物に増改築を加えて住みました。
一人っ子だったので、家族は両親と祖父母と犬でした。
私が37歳の時、母が亡くなりました。
もしかしたらもっと覚悟が出来たかもしれないのに、私の中で「死」というものが理解できていなかったこともあり、入院1週間後の、文字どおり「突然の死」でした。
この時は医者である父もいて、父もまた、母はまだ数週間か数日は生きていてくれると信じていたのだと思います。
何も理解できないまま、とにかく事務的な手続きや葬儀などを進めました。
しかし少し落ち着いたと同時に、今度はもともとあまりいい状態ではなく、母に心配されていた父が具合が悪くなりました。
約8ヶ月後に、今度は父が逝きました。
そしてこの時も、私にはまだ「死」をどう捉えたらいいのかわからなかったように思います。
父が自宅療養したがったこと、私にはそれを受け入れる余裕が無かったこと、それ以上に私が何か怒っていました。
まだ2歳に満たない娘を抱え、主人も巻き込み、主不在の病院、相続に関する様々なこと、お墓や法事のこと、そして自分の仕事、いままで抱えたことの無い様々なことがいっぺんに私の上に圧し掛かってきた、そんな気がしました。
自分が父に優しくしてあげられない事を気にしながら、どうにも出来ない感情、どうにも出来ない厳しい現実に振り回されて、大事なことが見えませんでした。
本当に「さようなら」なんだって、わかっていなかった。
元旦の早朝、病院からの電話で駆け付けた時には既に危篤というか、心臓マッサージでなんとか計器上では生きている状態。
お医者様に言われるまま、家族や親戚に電話して、父のベッドの横に戻ったと同時にお医者様は心臓マッサージを止めました。
そして死亡宣告。
元旦の朝はとっても美しい空気の澄んだ朝で、窓の外の遠くに広がる山々と空の青が印象に残っています。
入れ歯を外したままでアゴを固定されてしまったので、ちょっとお爺さん顔になった父はなんとなく別人のようだったので、まだ硬くならないうちにと、急いで入れ歯をはめました。
後で考えると、わざわざ心臓マッサージして、バタバタと電話したところで何の意味も無かった。
どうせなら静かに、じっくりと父の命が旅立つのを見届ければよかった。
もちろんお医者様だって、よかれと思って電話をするように促されたとわかっているけれど・・・。
やっぱり私が、わかっていなかったな~~、と思うこの頃です。
今でも時々父に優しく出来なかったことを悩みます、どうしようもないんだけれど・・・。
そして、仕方なかった・・・、と自分を慰めます。
その後に残された100歳前後の祖父母のことも、気がかりでした。
私は介護そのものはやらなかったけれど、中心になって介護をしてくれた叔母や叔父と協力しながら、祖父母も無事に見送ることが出来ました。
祖母の痴呆や施設のことなど、これまたずいぶんと沢山の問題がありましたが、今となってはもう笑い話です。
人間って、すごいな~と思います。
どんなに辛かったことも、過ぎてしまえば笑い話にまで出来てしまう。
それでいいんだと思います。
だから前を向いて生きていけるんだって。
祖父が亡くなった時、私と娘はバレエの公演を観に行っていました。あと3分早く叔母から連絡があればバレエは観ずに病院に駆けつけたと思うのですが、公演が始まる直前に携帯の電源を切ってしまったので、叔母からの連絡に気付いたのは遅めの昼食に入ったマクドナルドの中でした。
祖父の3週間後に逝った祖母の時は、早朝に病院からの連絡を受けて駆けつけ、叔父と従弟を呼んでずっと枕元にいました。
時々呼吸がゆっくりになり逝ってしまいそうになるのですが、「おばあちゃん!」 と声をかけるとまた呼吸が戻ったり。
祖母のひ孫に当たる子の出産の為に静岡に駆け付けた叔母に、従弟が電話している間も、祖母の呼吸が止まりかけたのですが、
「おばあちゃん、もう少し頑張っててね。もうすぐTちゃん戻ってくるからね。」
と声をかけると、また息を吹き返し、最後従弟が戻ってみんなで見守る中、少しずつ呼吸と呼吸の間隔がひろがって、最後にすうっと息を吐いて旅立ちました。
4人目の家族を見送る時に、初めて落ち着いて別れを告げられた気がします。
母にも父にも、祖父にも、こんなふうに見送ってあげたかったです。
4人の家族に、沢山のことを教えてもらいました。
でも、私はまだ介護ということはきちんと経験していません。
母は亡くなる直前まで幼かった孫と大人になりきれない娘の面倒を見てくれ、介護する間もなく逝ってしまいました。
父は前出のとおり。
祖父母は叔母が一手に引き受けてくれていました。
「死」については、ずいぶん考えさせられたけれど、まだ「介護」については、少し垣間見ただけです。
エリザベス・キューブラー・ロスの本に、ひとのお世話を散々してきた母上が、反対にひとからお世話を受ける立場になることを受け入れることが、大変難しかった、といったことが書かれていました。
きっと私も、介護についてもっともっと深く学ぶ日が来るのかも知れない、と思いました。